本書の目的
著者は、ブルーバックスから「山はどうしてできるのか」「海はどうしてできたのか」という本を出した。
それに続いて、
川の面白さの一つは、地形図を広げて眺めているだけで「どうしてこんなことになっているんだ?」という疑問が次々と湧いてくることです。それらの疑問を地質学のセオリーを駆使しながら解いていくのは、推理小説を読むように楽しいものです。およばずながら自分が探偵役をつとめ、川の謎解きを多くの人に面白がっていただけるような本が書いてみたくなったのです。
という目的をもって、川について地質学の観点から解説する本を書いた。

川をめぐる13の謎
世界の川について、13個のトピックをとりあげて解説していく。
印象に残った部分
川に関する謎が13個解説されている中で面白かったものを挙げてみる。
「砂漠の洪水」
涸れ川(ワジ)といわれる、「雨季にだけ現れる川」のことが書いてある。
雨季というものは、日本で住んでいると馴染みがないものなので、興味深かった。
涸れ川は、乾燥地帯にはよく見られる。

たとえばアラビア半島のオマーンの川は大部分が涸れ川である。
乾季のワジに水はなく、直径1m以上もの巨礫がたくさんn転がっていました。・・・これらの巨礫は、雨季のワジを轟々と流れていた泥水によって運ばれたものです。
涸れ川はときに洪水を起こす。
古代中国、後漢の武将がシルクロードの砂漠に入ったとき、突然川が氾濫した逸話が取り上げられている。
砂漠以外に、アイスランドのような北の雪国であっても、涸れた川にいきなり水が流れ込み、洪水が起きることがある。
夜の間は凍っていた場所にある雪や氷が、日の出から時間が経つにつれて融けていき、ついには洪水となるのです。・・・かかさかに感想した大地に突然、大河が押し寄せるさまは、きれいに磨かれて摩擦が少ないフローリングの床に水をこぼしたようなもので、水は下に浸み込まず、あらゆる方向へ核酸します。しかも、あとからあとから流れが押し寄せてくるので、水平面に薄くたまった水は非常に強い勢いで、どんどん先へと移動していくのです。
砂漠では突然洪水をしたり、突然のことで川や湖が消えることもある。
古代シルクロードに有った楼蘭という国は、湖の隣にあり繁栄していたが、湖が消滅したことによって急速に衰退した。
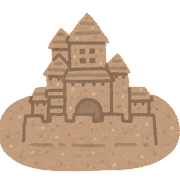
このように、同じ「川」であっても、乾燥地帯では日本などの風土とかなり異なった性質を持つ。
このように砂漠という特殊な条件下では、川は突然、氾濫したり、消滅や移動を繰り返したりと、じつにミステリアスなふるまいを見せるのです。
感想
川の流れは、人間の人生の長さからはほぼ不動であるような気がするが、
数百年、数千年以上程度の時間スケールで見れば、「川」というものはどんどん流れの変えるものであることが印象深かった。

「7つの謎」などのように多様なテーマを比較的短く解説していくというスタイルの本になっている。
そのため、途中で理解が難しくなったら別のテーマを書いてある部分を読むこともできる。

このあたりは、専門家ではない読者の立場に立って書かれていると思った。
本書の後半では、著者の川に関する仮説を3つあげている。
著者もことわっているように、確実な証拠があるわけではないシナリオが書いてある。
これらは「大胆な仮説」であるそうだが、自分としてはどの程度、現在の主流の学説と整合的なのか、そうでないのかはわからない。
いずれにしても、川の起源に対しては、大胆な仮説が出せるくらい、まだ解明されていないことが多いのだろうと感じた。
おすすめの読者。
川に関する科学に興味がある人。
本書中盤で詳しく解説される「多摩川」の周囲に土地勘がある人は、内容をより身近に感じられると思う。
川のトンネル工事に関する話も多いので、土木事業に興味がある読者にとっても面白いと思う。
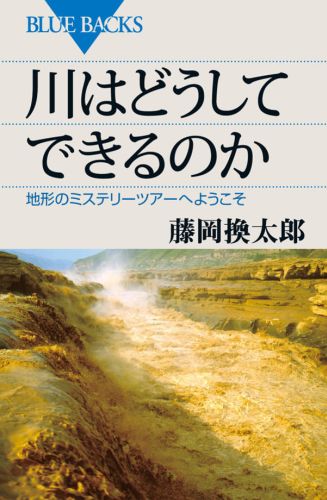
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849bd9.ec71f967.1a849bda.248a1e1f/?me_id=1278256&item_id=13775720&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6247%2F2000002576247.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F6247%2F2000002576247.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント