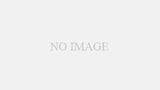概要
能力や考え方、性向などが生まれつき決まっている事が多いという内容。
現代のスタンダードな考え方では、生まれつき変えられないものを言及することは差別につながるので避けるべきとされている。

いっぽう、人間は生物の一種である以上、個体によって生まれつきの差があるという事実もある。
本書は、生まれつきの能力・知能・反社会性などについて、最近のさまざまな研究者が発表してきた成果を一般の読者向けにまとめた本。
印象に残った点
ボノボについて。
ボノボ(ピグミーチンパンジー)は、本書で乱婚の霊長類の例として何度かとりあげられる。
ネットでボノボの動画がたくさんあるので、見てみた。
ボノボを飼育している人は、まるで人間に対するようにボノボに対しているように見える。しかし・・・
ボノボは見た目は人間ぽいが、いくら知能が高いからといっても飼育する際に人間を襲わないと保証することはできない。責任もとれないということで、自分だったら飼育はこわくてできないな。と思ったりした。
現代人の「伝統的社会」
文化人類学で原始的な伝統的社会の部族の調査をしたとしても、それは人類が長いあいだ過ごしてきた「旧石器時代」の生活とは異なる。という指摘が興味深かった。

・・・人類の歴史のうち200万年は狩猟採集の旧石器時代で、ヒトの本性はこの長い期間に進化した。・・・私たちは、無意識のうちに農耕社会や歴史時代を基準に「人間」を理解しようとする。・・・文化人類学はたしかに多くの伝統的社会を調査したが、これは旧石器時代とはまったくちがう社会だ。旧石器時代のひとびとは、血縁関係を中心にした50人から100人程度の集団をつくって平地を移動しながら狩猟採集生活を送っていた。
現在の伝統的社会は、濃厚に適した土地を奪われたあとに島や密林などの僻地に取り残されたひとびとで、移動の自由を失って定住する以外になくなった。
現代でも文明から距離をおいた伝統的な生活をしている人たちが僻地にはいるが、そういう人々であっても旧石器時代の人間の「伝統的な本能」からは離れた生活をしているのだ。
これは意外な点だったが納得ができた。
おすすめの読者について。
遺伝や美貌、人種といった、個人の努力ではどうしようもないもの 生まれつき決まったもの によって人生が決まってしまうというのは現在の規範からすると都合が悪いことではある。
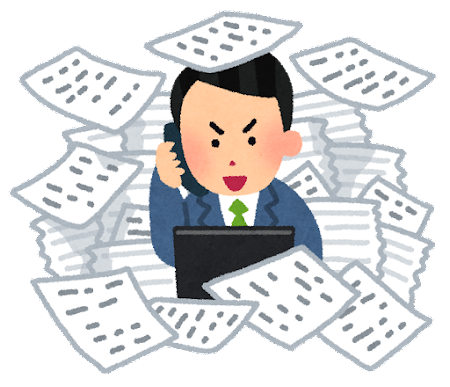
しかし、現代社会で頑張りすぎている読者にとっては、自分の能力や運命を「受け入れる」ことに役に立つのではないか。
現代では、生まれつきの欠点を克服しようとして努力し、その結果疲れているような人々も多いと思う。そういった読者には、本書のような本が良い気分転換になると思った。
まとめと感想。
本書は「進化生物学・進化心理学」という学問を用いて、人間の生態が動物たちと共通していることを説明する。
そして、現代のさまざまな社会現象や差別、遺伝に関するデリケートな問題を読み解いている。
著者は、お金の本を出して有名になった作家だと思ったが、本書では生物学に関する文献も読み解いている。

著者は頭が良く、また効率的な取材や学習活動をしていると思われるが、どのような資料収集方法を用いているのか気になった。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=17874685&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6637%2F9784106106637.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)