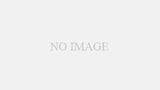日本のサラリーマンという働き方は特異である。という主張をする本。
本書ではこうした「不愉快な事実」(日本のサラリーマンの生産性が低いこと)を出発点にして、「日本人の働き方はこれからどうなっていくのか?」「急速に変わりつつある世界でどのように生き延びればいいのか?」を考えていきたいと思います。
という感じで、未来をどう生きていけばいいのか。を考える本。

内容は、日本流「サラリーマン」という働き方の問題点を指摘する。また、日本の「戸籍」と国籍・在日外国人に関連する問題の指摘をする。
働き方 4.0 とは。
1.0 年功序列、終身雇用。
2.0 成果主義
3.0 プロジェクト型
4.0 フリーエージェント。ギグ・エコノミー
5.0 機械がすべての仕事を行う。
現在は働き方を「 2.0 にしよう」という呼びかけが行われてるのを見る。
なぜ働き方 2.0 と 3.0 を飛び越えて、一気に 4.0 なのか?
官民挙げて「改革」しなければどうにもならなくなっている。
・・・しかし問題は、働き方2.0を実現したとしても、それではぜんぜん世界の潮流に追いつけないことです。最先端の働き方は、3.0から4.0に向けて大きく変わりつつあるからです。
「会社と管理職」の今後。
現在はギグ・エコノミーが流行している。
しかし著者の考えでは、映画産業でも映画会社が存在しているように、未来 会社も管理職もなくならないだろうという。

ブロックチェーンの「スマートコントラクト」で会社のような機能を持てるのではないか?と期待する人もいる。
しかし、著者は将来も会社は存在し続けると予測する。
マカフィーとブリフィルフソンの意見を引用する形で示す。
会社が存在する根本的な理由のひとつは、市場参加者が必要に応じてその都度集まるやり方では完備契約が結べないことにあります。現実の世界では、将来想定外の事態が起きたとき、誰がどうするかが決まっていないということはしばしばあります。会社が資産を所有していれば、不完備契約であいまいなことについて残余コントロール権を行使できます。会社は、契約に明示されていないすべての決定権を経営陣に与えるというかたちでやっかいなホールドアップ問題を回避しているのです。
戸籍制度の問題点。
著者は戸籍制度の問題点を批判している。戸籍制度に関連して、フィリピンの「新日系人」と呼ばれる仕組みをもとに著者は小説も書いている。また、「在日問題」も戸籍制度ゆえに起きたと言う。
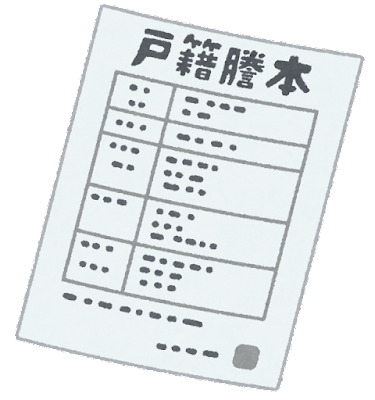
ほとんど指摘されませんが、こうした「在日問題」は戸籍制度ゆえに起きた戦後日本の「恥部」です。
在日外国人は、制度を悪用する事例が起きる一方で差別されたこともあった。
在日の一部にこの制度を悪用した者がいたことはたしかです。日本人なら本名でしか銀行口座を解説できませんが、過去には複数の「通名」で口座開設することができました。・・・在日なら外国人登録証の通名を変更するだけです。・・・
戸籍制度があるため、社会保障がイエ単位になっているので社会保障の持続性にも影響があるという。
日本の役人は、「戸籍」という名称や、戸籍を個人単位ではなくイエ単位で編成することなどを、総司令部による追求をかわしつつ守りきりました。その結果日本では、年金や健康保険などの社会保障もイエ単位になってしまいました。・・・
自分はイエ制度の特徴についてよく知らないので、また今度調べてみようと思った。
面白い・意外に思った部分。
・好きなことで生きていかないといけない世界は、「残酷な世界である。」と述べている。自分はその理由が読んでもよくわからなかったものの、個人によって教育の限界があるということなのかなと思った。
・遅刻してくれて、ありがとう。という本の内容をけっこう詳細に批判しており、意外性があった。
感想
・現代社会で会社員として働くときに感じるときのつらさを文章化している。
・会社の人間関係がなぜつらいのかを、理論的に理解したい読者が読むといいのかも。
・いっぽう、本書後半では高齢になっても働ける事例を紹介しており希望も持てる。
・最近の外資系IT企業を中心にした労働関連のカタカナのビジネス用語が要領よく解説されていく。ビジネス用語が素早く学べる。
・この著者独特の書き方で、「グロテスクな○○」という表現がちょくちょく出てくる。しかし意味がよくわからない。「グロテスクな社会」などとして使われる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=19517893&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1007%2F9784569841007_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=20238881&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9968%2F9784532199968.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)