ジョブ型とメンバーシップ型雇用という言葉を、新聞やニュースなどを通して聞くことが増えてきた。
著者は、労働関連の法律を専門にする学者であり、ジョブ型雇用という言葉を作った人らしい。
ジョブ型雇用とはなんとなく新しい働き方のキーワードなのかな?と思ったので読んでみた。

ジョブ型と成果主義との違い。
本書の書き出しは、新聞の記事が「ジョブ型雇用」の意味を誤解して使っているという批判から始まる。
・・・この解説記事を書いた日経記者はそのことに無知なようです。・・・職務定義書(職務記述書)を「ポストに必要な能力を記載」と説明しています。冗談ではありません。職務記述書は「能力を記載」などしていません。職務を記述しています。その職務がどういうタスク(課業)からなっているかということを記述しているのです。当然のことながら職務(ジョブ)には必要な技能(スキル)が対応しますが、これは日本的な職務遂行能力とは全く異なるものです。先ほどのネットメディアと同じように、ヒト基準とジョブ基準を混同していることを露呈しています。
と、厳しい批評だ。
世の中では「ジョブ型雇用とは、成果を重視する働き方だ」という誤解があるが、実はそうではない。メンバーシップ型雇用であっても、成果を重視することは多いという。

いっぽう、ジョブ型雇用の場合は「採用時」に能力評価が行われるが、ジョブにはめ込んで採用した後は基本的には成果は行われないという。(経営者などのジョブ型雇用を除く。)
・・・そもそも普通のジョブに成果主義などはなじみません。例外的に、経営層に近いハイエンドのジョブになれば、ジョブディスクリプションが広範かつ曖昧であって、・・・その成果を事細かに評価されるようになります。・・・
この点が ジョブ型雇用に関して 世間や新聞が誤解している(と著者が思っている)点であり、本書の主題である。
これに対し、日本のメンバーシップ型社会においては、・・・末端のヒラ社員に至るまで事細かな評価の対象になります。・・・彼らは何で評価されているのかというと、・・・特殊日本的意味における「能力」を評価され、意欲を評価されているのです。・・・この「能力」という言葉は要注意です。・・・
以降、本書ではさまざまな労働問題がジョブ型とメンバーシップ型雇用の形態に関連して書かれている。雇用に関する論点の奥の深さを感じることができた。
職業訓練
ジョブ型雇用社会では職業訓練は無償であるべきだ。という考え方がある。
こういうメンバーシップ型にどっぷり浸かった主流はとは隔絶した終焉的世界に、世界標準に近い職業教育訓練を公的に賄うべきという世界がひっそりと残存しています。高学歴になればなるほど縁のない、日本社会ではずっと非主流派の悲哀を味わってきた世界、公的職業訓練の世界です。公共職業訓練は無料です。・・・
公的職業訓練と大学を比較した部分で、現在の大学への批判をしている。
依然としてエリート教育時代に夢を追って、大学とは・・・「学術の中心として、・・・」のであるから、職業訓練校のようなものにしてはならない、と頑固に主張するアカデミズム思想です。
同世代人口の過半数が進学する高等教育機関が、職業教育訓練とは無関係の純粋アカデミズムの世界を維持できていたとすれば、それはその費用が親の年功賃金で賄われていたからであり、しかも、入社後は会社の命令でどんな仕事でもこなせるような一般的「能力」のみが期待されていたからでしょう。・・・企業側の人事政策が、その中身自体は何ら評価されていないにもかかわらず、アカデミズムがあたかも企業によって高く評価されているかのような(大学人たちの)幻想を維持していたわけです。
大学教育の社会的な役割を、大学で教育に携わる人がしっかり考えていないという趣旨だろうか。
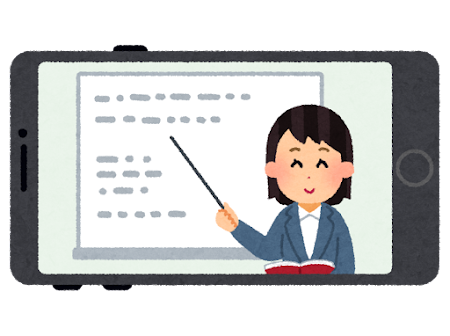
また次のようにも述べている。
日本型雇用に基づく親負担主義に支えられていた幻想のアカデミズムは今やネオリベラリズムの冷たい風にさらされて、有利子奨学金とブラックバイトという形で学生たちを搾取することによってようやく生き延びようとしているようです。そのようなビジネスモデルがいつまで持続可能であるのか、そろそろ大学人たちも考え直したほうがいい時期が来ているようです。
日本型雇用と、大学の仕組みとを結びつけて議論できるというところが面白かった。
さまざまな労働問題
ジョブ型・メンバーシップ型の雇用の理論以外にも、日本の労働問題のさまざまな点に関する現状分析がおこなわれている。
・管理職、転勤
・非正規労働者
・家族手当、児童手当
・女性活躍
・外国人雇用
・労働組合、労働争議
ただし、自分は大企業で管理職になったり、外国人雇用や育児休暇・労働組合の問題で悩んだりした経験がないのでよく分からなかった。

このような問題に実際に直面したことがある人は、本書の後半も興味深く読めるかもしれない。
感想
「日本の労働と欧米の労働」を対比・比較し、日本の労働の方法がいかに特殊であるかを示している。
いっぽう、同時に読んだ別の労働関連の本では、「日本の労働は世界の中でそれほど特殊性はない」ということを書いており、見方が違っているところが面白かった。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=20434503&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8941%2F9784004318941_1_4.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


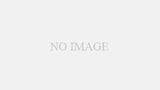
コメント