本書では、福井県「水月湖」の湖の底にたまった泥の層「年縞」の研究を通して、過去の10万年の気候の研究を行う。
類書には、岩波科学ライブラリー「時を刻む湖」がある。
地球温暖化が問題となるなかで、著者は「過去の気候」の研究を進めている。
水月湖の特殊性。
福井県の水月湖は、2012年まではほとんど無名であったが、気候研究に有用な堆積物である「年縞」が見つかり、現在では研究者の間では世界的にとても名前が知られた湖となった。
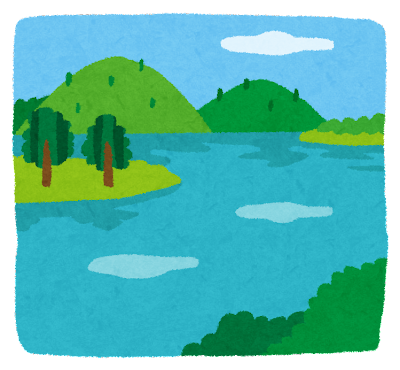
三方五湖は、流れ込む川がないため、湖底に酸素がないため生物活動がなく、温度の条件も揃って水がかき混ぜられない。これらの条件が重なったため、過去7万年分の生物活動が縞模様(年縞)となって湖の底にたまっている。
過去気候の復元。
本書の第五章では、著者が水月湖等の研究をもとに太古の「風景」を再現するようすが描かれる。
15万年前頃には、水月湖の周辺にスギはまったく生えていなかった。それが13万年前頃から急増して、12万〜11万年前頃にピークに達する。
・・・スギは大きく2回の増減のサイクルをくり返している。
このように得た過去の水月湖の気候変動のようすは、南極の「氷床コア」研究から得た結果と一致するという。またそれは、天文学的な地球の運動とも整合的であるらしい。

過去の水月湖周辺を復元したイラストも多く描かれており、楽しい。
第六章、第七章は、「古代の気候を復元する手法」の執筆時点における最新の手法について話されている。専門性が高いと思われ、自分はよく理解できなかったが、将来また戻ってきて読み直してみたい。
感想
湖の底にたまった堆積物から過去の気候を推理していく古気候学者、その思考過程や(地味な)研究風景が描かれており興味深かった。

福井県水月湖付近の過去の気候は、著者によればスギの多い時代、シラカバが多い時代、などと分類される。
人間社会では「十年の計は木を植うるにあり・・・」という言葉があるように、樹木は人間と比べてとても長い寿命を持つわけだが、さらにその樹木が長い時間の間に気候変動とともに勢力を増やしたり、減らしたりする。

このように長い時間のことを考えることで、現代の多忙な日常を忘れられる気がした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=18344484&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0043%2F9784065020043.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=17609885&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6427%2F9784000296427_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
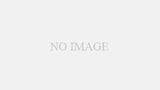
コメント