本書では、フェイクニュースの問題について考察している。しかし、単に「うそのニュースを見分ける方法」を紹介するのではなく、「私たちはどのように事実を認識するのか」という、より根本的な問いを掘り下げる。これは、歴史上多くの哲学者が探求してきた深遠なテーマである。現代では、SNSやインターネットの普及によって、この認識の問題に新たな視点が加わっている。まずは本書の内容を簡単に見ていきたい。
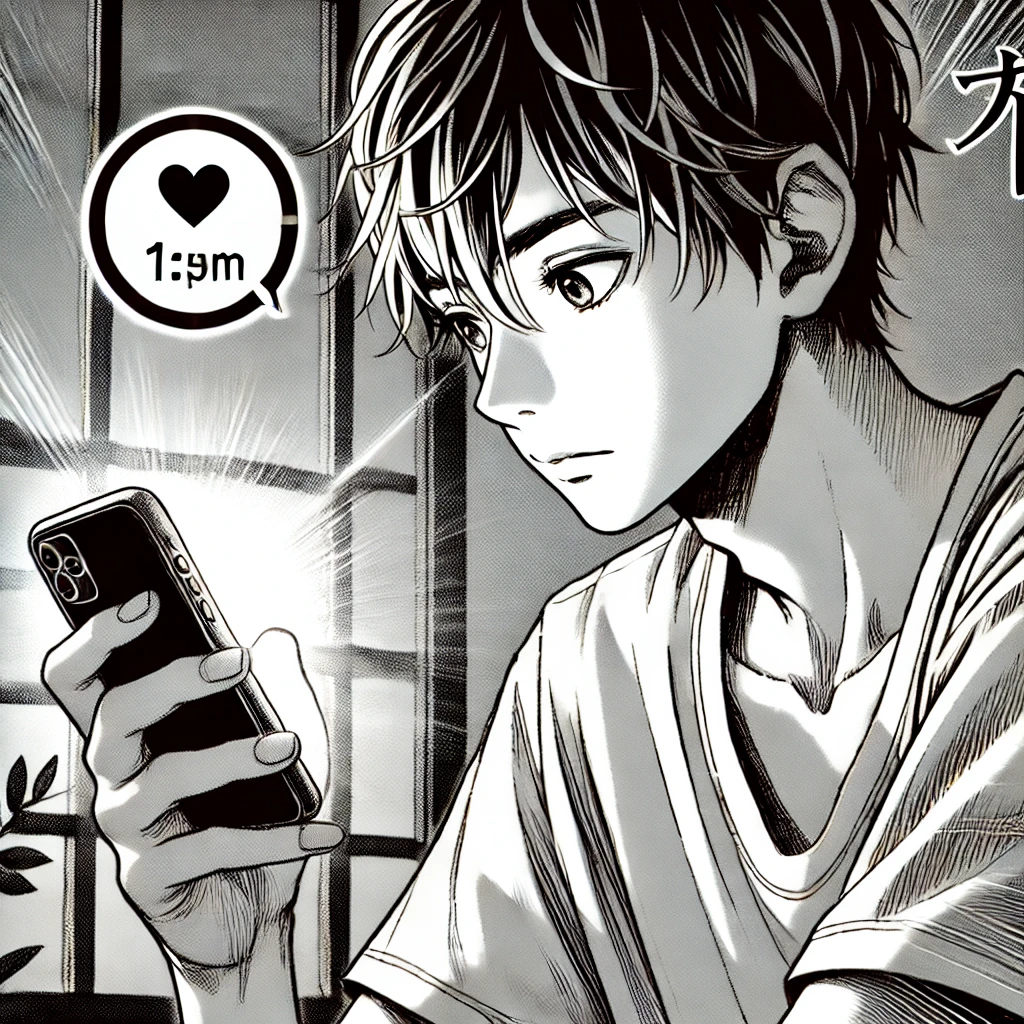
なぜ真偽に関心を持つべきなのか?
一般常識では、真実を知ることを重視することは至って当然のように思える。しかし、本書では哲学らしく、「本当に真実を知ることは必要なのか?」という問いを掘り下げていく。
考えてみると、常に真偽を追求することが必ずしも良いわけではない場面もあることがわかる。本書では、「真偽を重視すべき立場」と「そうではない立場」の両方の議論を取り上げている。
真実を重視すべき理由
真実ではない情報が広まることで、実際の被害が生じる。
(中略)
たとえば、感染症についての間違った情報であれば、それは生命の危険をもたらす。
「このきのこは食べられる」という信念が間違っていると、その信念に従って行為すれば死んでしまう可能性がある。
こうした「結果の価値」によって、真理の重要性を説明できる。一方で、真実を知ることが必ずしも幸福につながるとは限らない。
自分の病気が深刻なものであると知ることは、大きな恐怖や不安をもたらす。したがって、この場合も知らないほうが結果的に幸せに過ごせるかもしれない。
真実を伝えるニュースを知ることは、ときに不快な思い、不安、悲しみ、怒り、等々さまざまなネガティブな感情を引き起こす。
(中略)
真実は常に人に幸福や利益をもたらすとは限らない
つまり、真実が必ずしも人に幸福や利益をもたらすわけではない、という視点もある。
いっぽう、真理には、結果的な価値だけでなく、それ自体に価値があるとする議論もある。たとえば、哲学者 M.リンチ は、真理の 内在的な価値 を認める立場をとる。
「理解」と「納得」
本書では、「理解」と「納得」という二つの異なる状況が描かれている。納得 とは、「なぜ?」という問いに対して、「わかった」と思える説明が与えられることを指す。このとき、必ずしも真偽を強く意識するわけではない。たとえば、ある説明が論理的に筋が通っていて納得できたとしても、それが本当に真実であるとは限らないのだ。
この考え方は、Kvanvig (2003) の『なぜ理解なのか』 という議論と関連している。
われわれはさまざまな事象に対して「なぜ・・・なのか」と問いたくなる知的好奇心をもっており、理解できない現象を理解できるようにしたという欲求をもっている。
しかし、現実には次のようなことが起きる。
「なぜ」という問いに対して、自分が「わかった!」と思える答えを求めているだけで、そのうわさが事実かどうかにはあまり関心がない
例えば、大きな地震があったとき、「なぜ」起きたのか? という問いに対して、人工地震である、と言う説明が広まることがある。
しかしこの問いを抱く人のなかには、理解を求める人と納得を求める人がいる。前者は人工地震のうわさに対して真偽を問い判断するが、後者は自分が納得できればよいので、そもそも真偽にはあまり関心がない。おそらくこの違いが、納得を重視する人に対して、証拠による反論(反証)が困難である理由にもなっている。
たとえば、「私はなぜ病気になったのか?」という問いに対して、
「前世の行いが原因だ」
「親族の行動が影響している」
といった説明があれば、いくらかの人は「なるほど、そういうことか」と納得するかもしれない。しかし、これらの説明が科学的・客観的に正しいかどうかを確かめることは難しく、そもそも真偽を検証しようとする意識が働かない場合も多い。
うわさは信じてもいいのか?
「うわさを信じてもいいかどうか?」という問いに対するシンプルな答えは、「うわさの種類による」だろう。しかし、本書ではこの問題を掘り下げ、理屈を考察している。

本書では、「うわさは信じてはいけない」 という立場と、「うわさは信じてもよい」 という立場、両方が紹介されている。
うわさは信じてはいけない(オルポートの実験)
オルポートの実験は、社会心理学の研究として有名である。彼の研究によれば、うわさは人から人へ伝わる過程で単純化され、情報内容が変化する。たとえ、個々の人が誠実に発話していたとしても、伝言を繰り返すうちに、最初の情報とはまったく異なる内容になってしまうことがある。 したがって、「口伝えのうわさは信じるべきではない」というのが、オルポートの研究の示唆する結論である。
うわさは信じてもよい(哲学者コーディの議論)
一方で、哲学者コーディは反論を展開している。
彼の議論によれば、聞き手はうわさの正しさを見極めるための手段を持っている。うわさの正しさを見極めるために、次のような方法がある。
- 事前知識を活用する
- うわさを伝える人の関係性を考慮する
- うわさの伝え方や確度に関する情報を精査する
- 異なる情報源にも当たる
このように、単純な「伝言ゲーム」と、実際の社会でのうわさの伝達は同じではない。
どちらの議論にも説得力があるが、現代のSNSがこの問題をさらに複雑化している。SNSでは、うわさの発信者が誰なのかが必ずしも明らかでなく、情報の信頼性を判断するのが難しい。
この状況は「文脈の崩壊」と呼ばれる。SNSには文字数制限があるため、情報が簡略化されがちであり、そのことが誤解や誤情報の拡散を助長する要因となる。
陰謀論は信じてもいいのか?
この問いに対する一般的な答えは、「陰謀論の種類によるが、基本的には信じられない」というものだろう。本書では、陰謀論の特徴を整理し、また陰謀論を信じる心理についても考察を試みている。
本書では、次にあげるような人々による、陰謀論の考察を取り上げている。
K.ポパー(1972年)—「社会の陰謀論」
ポパーは、陰謀論とは、かつて神の意志によって説明されていたものを、資本家や帝国主義者、特定の秘密結社などに置き換えたものであると主張した。例えば、「シオンの賢者」といったユダヤ系の陰謀説がその典型例である。
また、陰謀論には「社会の出来事がすべて事前に意図された計画通りに進む」という特徴があると指摘する。現実の社会は複雑な要因が絡み合って動いているが、陰謀論を信じる人々はその複雑さを理解せず、単純な因果関係を求める傾向があると論じた。
ピグデン(1995年)
ピグデンは、ポパーの議論を批判し、「誰も主張していないことを批判している」と指摘する。つまり、世の中のあらゆる出来事を陰謀によって説明しようとする人は実際にはほとんどいないのではないかという主張だ。
実際に成功した陰謀も歴史には存在する。例えば、カエサル暗殺、リンカーン暗殺、スノーデンによる米国政府の告発、これらは、単なる憶測ではなく、歴史的事実として記録されている陰謀である。そのため、すべての陰謀論を一括りに否定するのは合理的ではない。
R.ブラザートン(2014年)
ブラザートンも陰謀論を論じた。ブラザートンは、陰謀論を 「相対的にもっともらしくない陰謀の主張」 と定義した。しかし、このように陰謀論が不合理であることを定義に含めてしまうのは「論点先取」である。
ブラザートンは心理学者であり、陰謀論そのものの論理性というより、「陰謀論を信じる人の心理」にも焦点を当てた。彼の研究によると、陰謀論を信じる人には以下のような認知的傾向がある。
- 偶然の一致を偶然とみなさず、そこに意味や意図を見出す
- 確証バイアス(自分の信じる情報ばかりを集める)
- 比例バイアス(大きな出来事には必ず大きな原因があると考える)
Q.カッサム
カッサムは、陰謀論の定義そのものが曖昧であり、何が陰謀論で何がそうでないかを明確に区別するのは難しい」と指摘した。彼の議論によれば、陰謀論への対処法としては、次のような方法がある。
- 反論(論理的に誤りを指摘する)
- 暴露(誤情報の出所を明らかにする)
- 教育(陰謀論に騙されにくいリテラシーを高める)
しかし、これは「黙っていないで反論することが重要」という、ある意味で当たり前の結論に帰着するので、本書ではやや物足りないものとして扱われているように思う。
呉座勇一
日本の歴史学者である呉座勇一は、日本の中世史研究においても、陰謀論的な説明が紛れ込むことがあると指摘した。彼は、陰謀論の特徴を以下の4点で整理している。
- 関係性の単純明快すぎる説明(実際は複雑な要因が絡んでいるのに、一部の人物や組織の計画とする)
- 論理の飛躍(証拠が乏しいのに断定的な結論を出す)
- 歴史的文脈を無視する
- 感情的な物語を重視する
例えば、「応仁の乱」のような歴史的事件は、単純な因果関係で説明できるものではなく、多くの政治的・経済的背景が絡んでいる。
ニュースに対する哲学的な態度・・・判断保留という方法
本書では、ニュースに対する姿勢として「哲学的な態度」を考察している。その中で、ウィトゲンシュタイン の言葉が引用されている。
このような真理への探求には時間が必要である。大量の情報に素早くアクセスすることを可能にしたインターネットは、情報収集にかかる時間を節約することでわれわれの考える時間を増やしてくれるのかと思いきや、むしろ一つひとつの情報とじっくり向き合う時間をわれわれから奪っている。
哲学においては、「とりあえず判断を保留する」「急ぎすぎない」 という態度が重要視される。
ここでおすすめしたいのは、急ぎすぎないことである。ウィトゲンシュタインは、哲学者同士の挨拶は「どうぞ、ごゆっくり」であるべきだと述べている。われわれは話し合いをしていても、つい結論を急ぎたくなり、何かの問題について考えていても、すぐに答えを知りたくなってしまう。しかし、そのような姿勢は哲学からもっとも遠いところにある。・・・真偽の判断をいったん留保してみることで、腰を落ち着けてその情報と向き合い、妥当性や信頼性を吟味する余地が生まれてくることになる。
とはいえ、ニュースには「即時性」が求められるため、受け取った瞬間に何らかの反応を迫られることも多い。社会的な出来事に対する意見を問われたり、判断を求められたりする場面では、「考える時間を取る」こと自体が難しくなることもあるであろう。
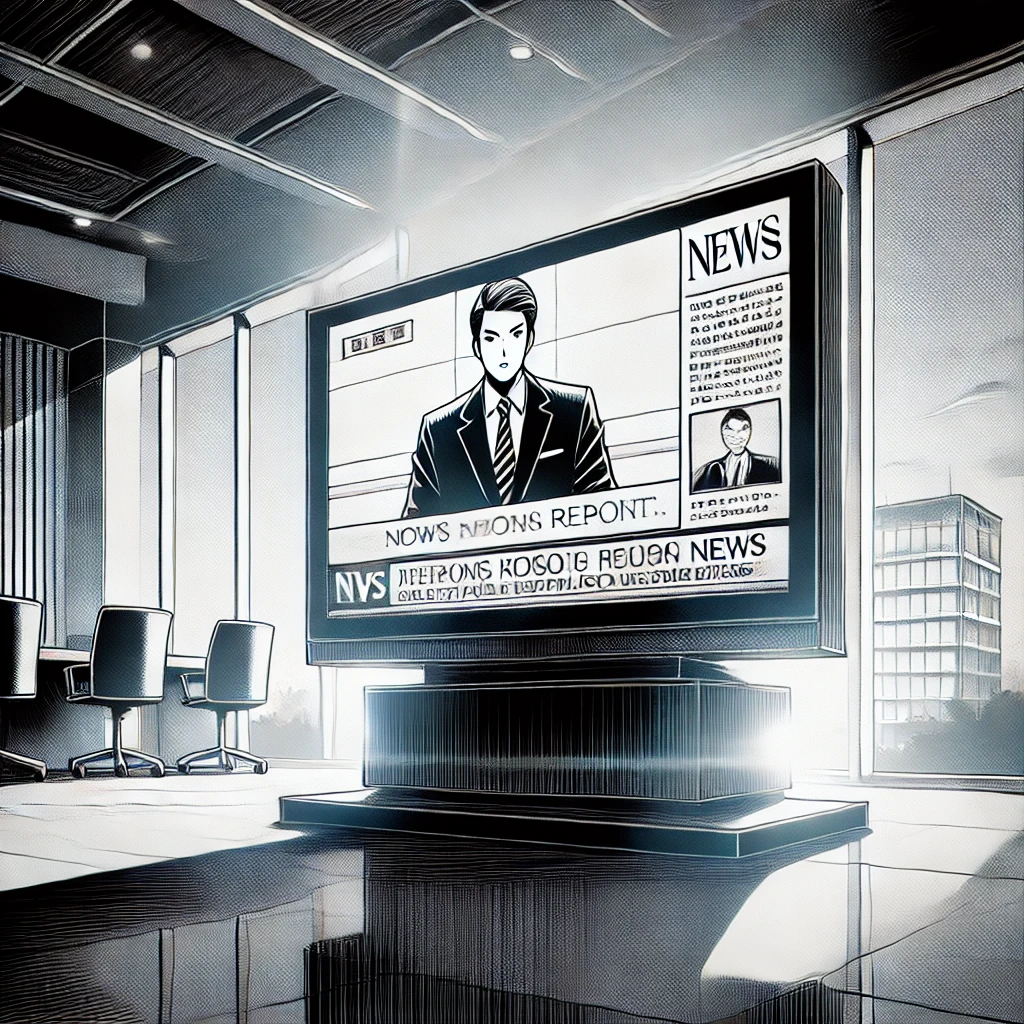
感想
以下では本書を読んだ感想を記しておきたい。
真偽と関心の違い
私たちは日常生活の中で、どれほど真偽を意識しているのだろうか。
考えてみると、私たちは何かを学ぶときに常に真偽を深く追求しているわけではない。科学的な根拠のない宗教や迷信に関しても、多くの人が「偽である」と認識しながらも、それを慣習として受け入れていることがある。
また、自分にとってどうでもいい情報 に対しては、そもそも真偽をあまり気にしない。たとえば、ニュースとは一般的に「遠くの県や遠くの国で何かが起きた」という情報である。それが多少誤って伝わっていたとしても、直接的に自分に影響が及ぶことは少ない。そのため、人々は事実の正確さよりも、面白さや感情を揺さぶる要素 を重視し、ニュースを「楽しむ」側面がある。
しかし、真偽が直接的に自分の重大な被害につながる場合 には、私たちは真偽を強く意識する。たとえば、
- 明日の天気予報(雨が降るかどうか)
- 仕事の取引先の担当者の変更(誰とやりとりするのか)
といった情報は、単に「面白いかどうか」ではなく、「正しいかどうか」が重要になる。たとえ仕事の取引先の「Aさんという社員が相手方の担当のほうが好ましい」と思っていたとしても、事実を確認せずに「Aさんが担当だ」と信じ込むことはないだろう。情報の重要性によって、私たちは真偽への関心の度合いを変えているのである。
科学の世界でも、「わかった」と感じることと、実際の真偽が異なることは少なくない。
本書では挙げられていない論点だが、次のような例を考えてみたい。たとえば、物理学のニュートンの運動法則 を学ぶと、多くの人は「わかった」と納得する。しかし、実際にはニュートン力学は厳密には正しくなく、より正確な理論として「アインシュタインの相対性理論」というものがある。つまり、「ニュートンの法則を理解した」と思っても、後にそれが完全な真実ではないと知ることになる。
このような場合、人は「わかった」と思うまでに多くの努力をしているため、その納得自体を疑い、さらに真偽を追求することは簡単ではない。自分が納得した理屈をもう一度検討し、それまで「理解した」と信じていたものを放棄して、「自分はまだわかっていなかった」と認めることは、しばしば、とても難しい作業であると思われる。
SNS開発について — 哲学的考察を応用する
本書では、SNSの利用者の視点に立った考察を行っている。そのため、SNSの運営側(プラットフォーム提供者)の視点 はほとんど取り上げられていない。しかし、哲学的な考察を踏まえることで、「では、どのようなSNSを開発すればよいのか?」 という新たな視点が生まれる。

SNSの開発目的と収益化の課題
「良いSNS」とは何か? 多くの場合、「収益化できるSNSを開発したい」 というのが現実的な目的になる。なぜなら、収益を生まないサービスは運営が継続できないからである。
現在のSNSの収益モデルの主流は、インプレッションを最大化し、より多くの広告を表示する ことにある。そのため、アルゴリズムはユーザーの関心を引きつけ、滞在時間を延ばすように設計される。その結果、必ずしも正しい情報が優先されるわけではなく、感情を刺激する内容が拡散されやすい。
本書の議論の中でも、「うわさの伝達経路」に着目することは、SNS開発のヒントになり得るのではなかろうか。
例えば、SNSの運営側は、発信者の信念がどのような経路で伝わったかを把握できる。その情報を活用し、以下のような仕組みを導入することも考えられる。
- 信頼性スコアの導入 うわさが複数の経路を通じて拡散された場合、その情報の表示回数をブーストする。ただし、これは誤情報の拡散を助長する可能性もあるため、慎重な設計が必要。
- うわさの「透明性」を高める仕組み 例えば、情報がどのような経路を経て伝わってきたのかをユーザーに見せる。これにより、ユーザーが情報の信頼性を判断しやすくなる。
- 「急ぎすぎない」SNSの設計 本書の哲学的視点に基づき、「すぐに反応しなくてもよい」SNSの設計も考えられる。例えば、投稿後すぐにシェアできるのではなく、「24時間後に公開される」仕組みを導入し、情報を熟考する時間を与える。
収益化の方法とSNSの方向性
本書では、SNSの収益モデルについては触れていないが、読者としてはこの点も考察を深める価値がある。
- 誤情報を広げないようなSNSを作る場合、収益モデルは成立するか?→ たとえば、ファクトチェックを強化したプラットフォームを提供し、信頼性を重視するユーザーに向けたプレミアムプランを設ける。
- 誤情報を許容し、「うわさを楽しむSNS」とするのも一つのアイデアではないか?→ 例えば、「都市伝説専門SNS」や「仮説を自由に議論できるSNS」など、エンタメとしてうわさを楽しむ場を提供する。これはかつて、紙媒体の雑誌にも似たような方向性のものがあったのと同じようなことである。
- ユーザー数が増えなくても良い、有料のSNSとする。→ たとえば、少数の専門家や知識人向けのクローズドなSNSを運営し、サブスクリプション制にする。
- SNSそのものではなく、別の収益源を設けるか?→ たとえば、SNSを無料で運営しつつ、特定のコンテンツやコミュニティ機能を有料化する。
「陰謀論」という言葉への違和感
個人的に感じたのは、「陰謀論」という呼び名が現時点では陰謀論の本質を正確に表していないのではないか、ということだ。
「陰謀」という言葉は、少数の人が密かに集まり、何かを企てる行為を指している。
だが、「陰謀論」とされるものの中には、必ずしも秘密裏に進められる計画ではなく、単に一般的な説明とは異なる解釈を主張するものも含まれる。そのため、「陰謀論」という名称自体が適切ではない場合も出てきている。
本書の中でも書かれていたが、「陰謀論」と呼ぶことで、その内容が最初から否定されるべきもの、あるいは荒唐無稽なものとみなされる側面がある。
つまり、「陰謀論」と呼んだ時点において、議論の枠組みが限定されてしまう可能性がある。陰謀論に関しては、より適切な呼び方を考えることも、今後の課題かもしれない。
まとめと将来
人間が「うわさ」や「ニュース」を楽しむ性質を持つ限り、この問題から完全に離れることはできない。 そして、インターネットの発展によって、情報の拡散と消費のあり方はさらに大きく変化していくだろう。
考えてみれば、「再投稿(リツイート)」のような機能も、もともとはユーザーが自然発生的に行っていた行為をTwitterが公式に実装したことが始まりだった。それ以前には、SNSにおいて「再投稿する」という概念自体がほとんど存在していなかったが、Twitterがこれを取り入れたことで、今や多くのSNSにおいて標準的な機能となっている。
このように、SNSの時代には、独自の発信スタイルや情報の伝達手段が生まれ、それがまた哲学者たちの考察対象となっていく。今後も新たな投稿形式や情報伝達の方法が登場し、それらが哲学的な議論の対象となるのは間違いない。
情報があふれる現代において、どのように真偽を判断し、どのように情報と向き合うかは、ますます重要なテーマになっていくだろう。SNSと哲学が交差するこの時代は、非常に興味深い時代だといえる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=21353454&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0333%2F9784004320333_1_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


コメント