著者の橘氏は、現代社会について、金儲け・遺伝・知能などをテーマに面白い著作を多数出している作家。
昔の哲学者は、精神や心の働きについて思索した。
しかし、こうした過去の偉人たちの思想は、科学が発展した現代から見ると時代遅れになっている部分がある。
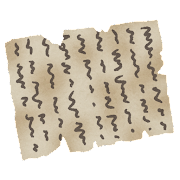
本書が発行された時期に、日本の大学を「L型大学・G型大学」に分けるという計画が発表され、
文系学者を中心に反対運動が起こった。著者は次のように、文系学者を批判する。
人文系の学者は、・・・人間力を鍛えるためには教養が必要だ」と反論している。たしかにこの”複雑で残酷な世界”を生きていくためには知力だけでなく人間力も大事だろうが、彼らは根本的なところで間違っている(あるいは、知っているのに黙っている)。それは、人文系の大学で教えている学問(哲学や心理学、社会学、法律学、経済学のことだ)のほとんどがもはや時代遅れになっていることだ。
過去の有名思想の中には、現代の視点から見ると古くて読む価値がなく、現代人があえて「読まなくてもいい」ものが多い、というのが著者の意見である。
時代遅れになっている哲学
19世紀ー20世紀に現象学と呼ばれる哲学をつくったフッサール。
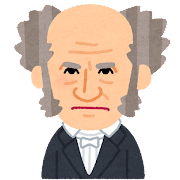
本書では、フッサールも批判の対象となる。
フッサールは、
哲学が科学に屈服する姿を見て「こんなことではいかん」と決意した
そして彼は現象学を打ち立てた。しかし、著者によれば
現象学というのは「科学に対する哲学の最後の挑戦」だった
とまとめ、次のように批判する。
フッサールは意識について一所懸命考えて難解な本をたくさん書いたけど、どんなにエポケーしても”諸学の基礎”になるような確実なもの(超越論的主観性)は意識のなかには見つけられない。なぜなら、そんなものは最初からないのだから。これではどんな壮大な理論も、土台のない大伽藍と同じだー残念でした。
そして、フッサールの後に現れたハイデガーについての評価は次のようになる。
ハイデガーの「存在と時間」はフッサールよりさらに難しくて、日本でも”秘教(カルト)的理論”が大好きなひとたちに人気がある。でも現象学はそこからどんどん先細りになっていって、いまではほとんど顧みられることもない。自然科学の立場から意識を研究するひとたちも、デカルトにはしばしば言及するがフッサールやハイデガーは完全無視だ。
現代科学から見て時代遅れになった哲学の書は読む必要がなく、脳科学に基づいて精神を理解するべきだ。という論調で、本書は書かれている。
異なる考え方の結びつき。
本書のなかで印象に残った部分。
一見して、対極にあるような考え方が親和的である ということがよくみられる ことが指摘されている。
米国の事例、人権・平等などを重視するリベラル派と、宗教的や価値観を重視する保守派(オルタナ右翼)が対立している。
それに加え、最近は「サイバーリバタリアン」も登場している。これらの関係は次のように複雑になっている。
サイバーリバタリアンの多くはシリコンバレーの起業家・投資家やエンジニアで、経済的にはリベラルよりさらに裕福でプアホワイトとはなんの共通点もないが、「政治的正しさ」ではなく「科学(テクノロジー)」を優先することでしばしばリベラルと対立する。すると、・・・プアホワイト(オルタナ右翼)とのあいだに連帯感のようなものができてくる。
科学的な思考をするサイバーリバタリアンは、実は保守派と考え方が似ている部分もある。
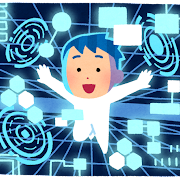
ここからサイバー・リバタリアンは進化論ときわめて相性がいいことがわかる。なぜなら、・・・進化論こそが社会や人間を説明する唯一の「科学」だからだ。
思想というものは単純に左と右に分類できるわけではなく、複雑なかかわりあいがあるということがわかった。
自分の考えとしては、人間が昔から自然に持っていた考え方を保守派と考えれば、自然科学を重視するサイバーリバタリアンと保守派の考え方が似ていることも納得できると思った。
感想
本書では心のはたらきに関する話題が多い。
いっぽう、数学・原子科学 などについても過去の哲人の著作を、本書のようなわかりやすい書き方で見直した本があったらいいと思った。そういった本があったら読んでみたい。
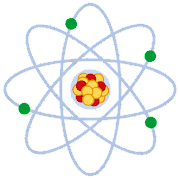
中盤では米国社会の問題を中心に書いている。(オルタナ右翼・黒人保守派など。)
身近ではないが、話として読むぶんには面白い。
では自分が住んでいる日本の社会では分断が起きているのか?興味を持った。
本書タイトルにもある「読まなくてもよい本」を選ぶ重要性について。
近年では、人々がどんどん情報収集に「効率」を求めるようになっている。
たとえば、
・本の要約をするウェブサイト
・動画サイトにおける倍速再生機能
などが出現している。
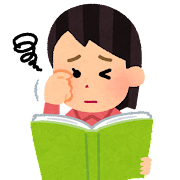
生きていくために必要な知識がどんどん増えていく中で、情報が多すぎてかえってつらくなる場合もあると思われる。
今後、「どの情報を学ばなくてもよいか」を選んでいく必要性が高まるだろう。
本書はそんな世の中への一つの試みとして意義が深いと思った。
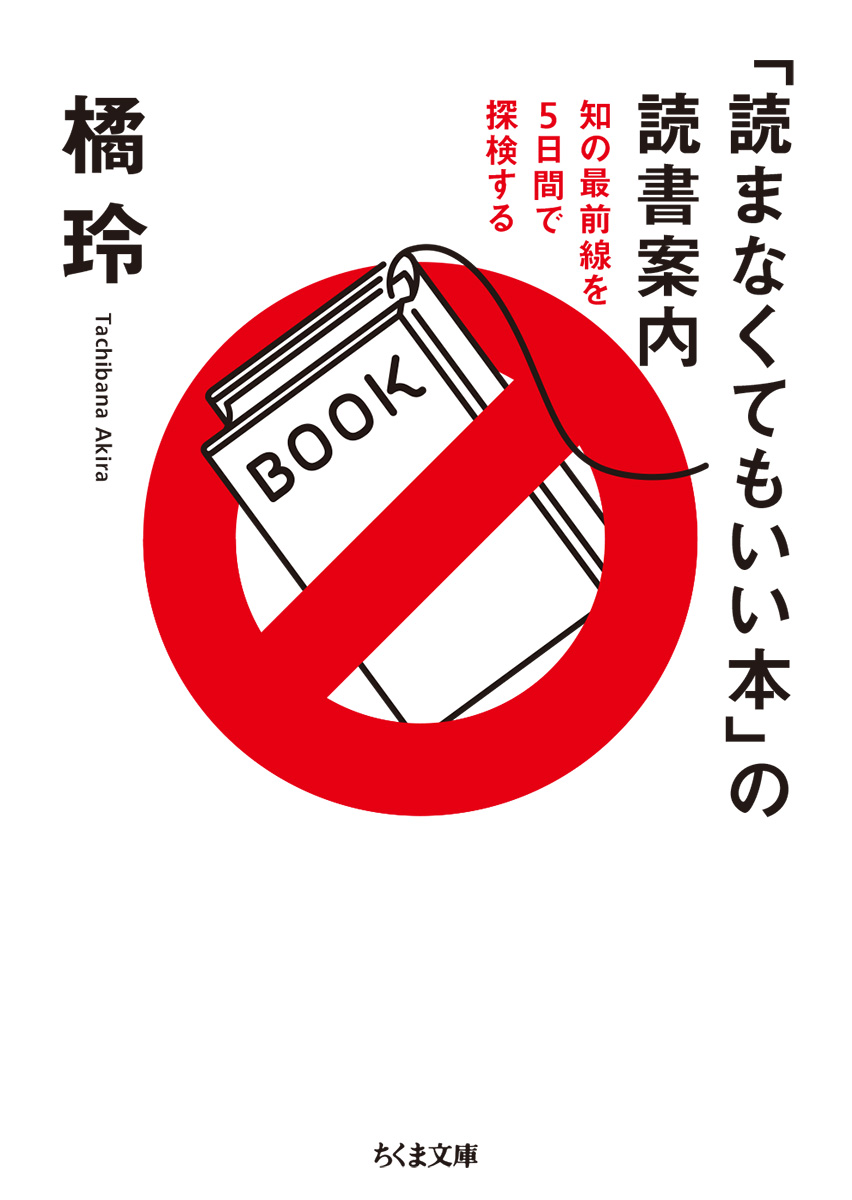
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=17657366&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6795%2F9784480816795.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6795%2F9784480816795.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)



コメント