高校生のときに国語の授業で『山月記』をやった。最近、再読してみたので感想を書いていきたい。本作は「転職」の良いたとえ話になっているので、社会人の経験をもとに「転職」「動物」という観点で書いてみたい。
あらすじのおさらい
さてこの物語の舞台は唐の時代の中国であり、李徴(りちょう)という青年は尊大な人物であり、秀才であり、若くして官僚になったが詩人を目指して官職を辞任した。その後、専業の詩人としては大成しなかったため再び地方官吏になったものの、かつて見下した同級生に仕えるのに耐えられず、ついに発狂して行方不明になった。翌年、かつて李徴の友人だった袁傪(えんさん)が偶然、「虎になった」李徴に出会う。そこで、李徴は自分がなぜ失敗したか、それは自分の性格のせいだというような長い告白をし、現在は人間の心を失いつつあると述べる。その後、袁傪との別れ際に、虎になった李徴は一度だけ自分の虎の姿を見せ、再び草むらに姿を隠し、「再びその姿を見なかった」。これが物語のあらすじである。

学生時代の第一印象
高校生の時に読んだときの感想は、正直に言えば「説教くさい小説」というものだった。また、無闇に漢語が多くて読みにくいと思ったのを覚えている。実際、本作は古文でも漢文でもないのに昔風の装いをしているのである。その格調の高さがむしろ鼻について、素直に文章に入り込めなかった。
また、本作では、虎になった李徴が自らを評して言う「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」という表面的には矛盾した表現が重要なキーワードとなっていくのであるが、これらは単純に「人を見下してはいけない」「同級生を軽蔑してはいけない」という風に読める。これだけ読むと文学というより「性格指導」という方向性を感じる。学校の授業であるので、こちらも常に指導の方向性を先読みしなければならない。それを考えるのが面倒で、息苦しかったように思う。
社会人としての再読
だが社会に出てから再読すると、少し違う物語が見えてきた。これを書いてみたい。
李徴が若くして官僚に登用されたのは、大企業にエリートとして就職したのと同じだろう。安定を嫌って詩人を志すのは、安定を捨てて夢を追うキャリアチェンジにあたる。しかし現実は厳しく、生活は苦しくなり、再び地方官吏になる。それは中小企業に再就職するようなものだ。しかも同級生たちはすでに出世しており、自分がかつて見下した相手の下で働かされる。
虎になるということ
ここで自尊心は徹底的に傷つき、やがて虎になる。虎になるというのは、ブラックな環境や怪しいビジネスの業界であり、環境の論理に染まってしまうことによく似ている。
新しい職場で「虎になる」とはどういうことだろうか? 例えば、プロジェクト全体の目標よりも自分のタスク管理を優先してしまう。追及されないように、仕事を残さないように動く。営業なら、ターゲットとなる顧客を定めて、狙いを定めて接触する。これらは虎の行動にそのまま重なる。群れず、忍び寄り、獲物を仕留める。
会社で生きる私たちは、知らず知らず虎の論理で動いている。李徴が語る「人間の心が短くなる」とは、会社の中の論理だけで考えるようになる状態だろう。社会や理想を忘れ、社内のルールと慣習に完全に適応してしまう。顧客の役に立つかよりも、上司に怒られないかを優先する。会社を出ると別世界のように感じるのは、人間の心が短くなっているようなものだ。
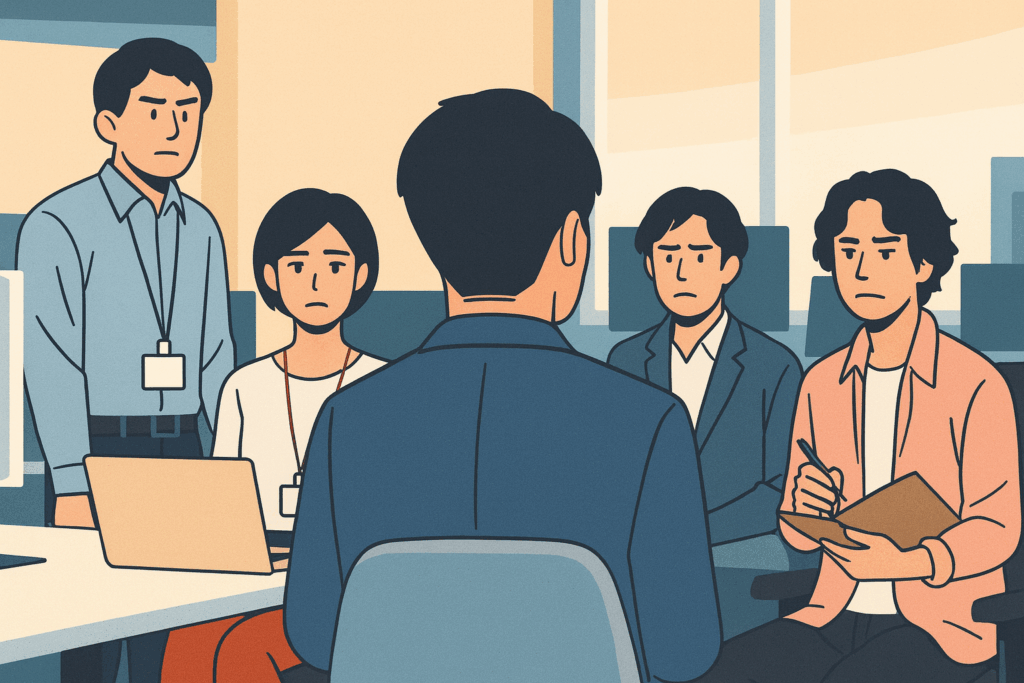
尊大さの意味
山月記は学生のころには「プライドが高くて尊大な人が罰を受けた」話だとしか思わなかったが、今読むと「尊大さ」は生き残るための武装だと理解できる。自信は外からは見えない。不安だからこそ人は強がり、尊大に振る舞う。李徴もまた、低い自己評価を覆い隠すために尊大に振る舞ったに過ぎない。実際、彼は「自分は宝石ではなく瓦ではないか」と恐れていた。つまり最初から自己評価が低く、それを覆うために尊大にならざるをえなかったのだ。そして虎になった後も相変わらず自己評価が低く、例の「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」という告白につながる。
なぜ虎なのか
では、なぜ虎だったのだろうか?
日本人である作者(中島敦)は、なぜ他の動物ではなく、日本には生息せず、読者がよく生態を知らないだろうと思われる「虎」を李徴にあてがったのだろうか?なぜ犬、猫、馬ではないのだろうか?
犬だったら忠実で協調的に組織に従う存在であり、李徴の同級生たちに重なる。馬だったら勤勉で持久力のある存在で、地道に努力を重ねて出世した人々を示すだろう。猫なら気ままで自由な存在で、李徴が猫になっていれば物語はもっと軽やかで幸福な結末を迎えたかもしれない。あるいは龍ならどうだろうか? 龍なら超越的な成功者であり、李徴が夢見た理想そのものであっただろう。
しかし、彼は虎になった。虎は猫と同じように単独行動をするが、猫と違って残酷で、人を食う捕食者だという印象がある。その二面性こそ、孤立した自尊心と残酷な現実に引き裂かれた李徴にふさわしいのである。
同じ捕食者であっても、もし熊ならどうだろうか? 熊なら、田舎に現れる危険な隣人のように描かれ、文学的な象徴性は弱まっただろう。サメなら血に反応する捕食者としてふさわしいが、舞台が山野から海に移ってしまい、『山月記』という物語の基盤は崩れる。さきほど見たように、龍や猫では悲劇性が薄れる。だからこそ李徴は、虎でなければならなかったのだ。
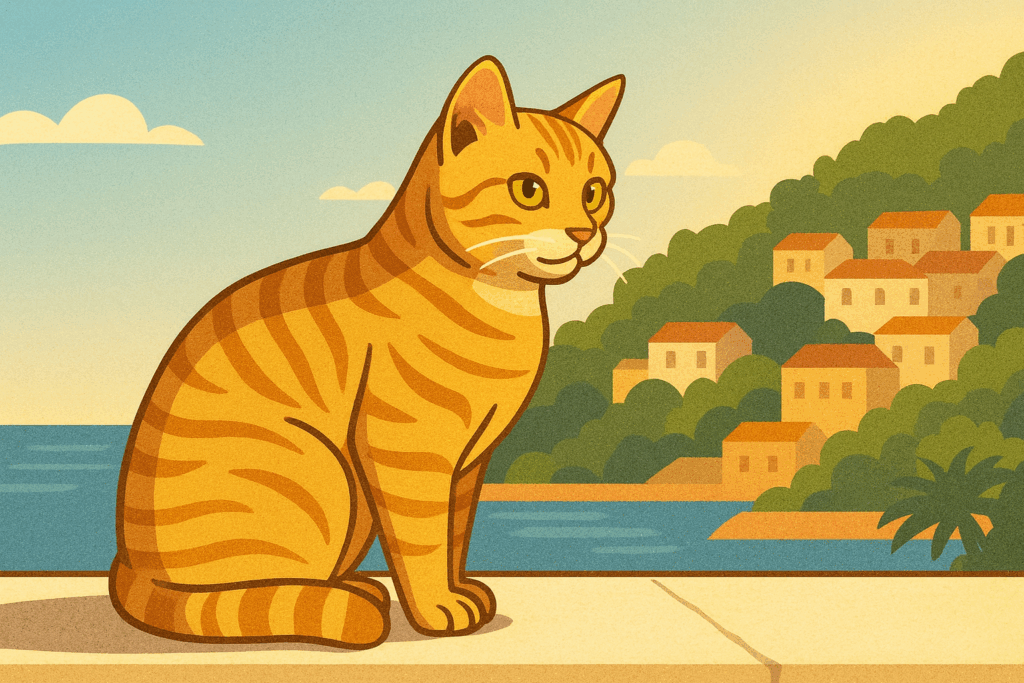
動物寓話としての山月記
このように、『山月記』は動物たちの寓話として読むといっそう理解が深まる。李徴は虎となり、同級生たちは犬や馬となり、もし別の選択をすれば猫や龍になれたかもしれない。現代社会に置き換えれば、安定を選んで組織に従う人は犬や馬であり、自由を求める人は猫であり、孤高に成果を追いながら人を食うように働く人は虎であり、圧倒的に成功する人は龍だろう。
大切なのは、どの動物が正しいかではない。ときと場合によって人は犬にも猫にも虎にもなれる。キャリアは固定されたものではなく、環境と選択によって常に変わるのだ。李徴の悲劇は特別なものではなく、誰にでも起こり得る。大企業を捨てて夢を追う人、中小企業に転職して苦しむ人、ブラックな環境に飲み込まれる人、協調して安定を築く人、自由に生きる人、圧倒的に成功する人。人はいつでも動物に変わる。
一方通行の運命論と現代社会
ただし、『山月記』を単なる転職の比喩としてそのまま読むのはキャリア教育上はよろしくないと思っている。その理由は、この物語は一方通行の物語であるからだ。李徴の物語は、一度道を踏み外したら終わり、という一方通行の運命論に貫かれている。官僚を辞めて詩人になれば挫折しか待っていないし、人間から虎になれば二度と戻れない。これは東アジア的な「一度失敗すれば取り返しがつかない」という社会規範をよく表している。
だが現代のキャリアは、それとはまったく異なる方向に進んでいる。今日では「リスキリング」や「人生百年時代」という言葉に象徴されるように、人は何度でも学び直し、別の職種や業界に挑戦することが可能になっている。ITエンジニアがデザイナーに転身することも、営業からNPOに移ることも珍しくない。むしろ、一つの会社で犬や馬のように勤め上げるよりも、虎や猫のように環境を変えながら柔軟に生きることが奨励されているのだ。
李徴の時代であれば、彼が虎になった時点で人間社会から追放されるしかなかった。しかし現代社会において「虎的な働き方」、つまり成果至上主義や孤立したフリーランス的なキャリアを選んでも、それを経て再び「犬」や「馬」のように組織に戻ることができるし、「猫」のように自由な道に進むこともできる。あるいは、新しいスキルを身につけて「龍」のように成功者へと変わる可能性すら開かれている。
したがって『山月記』をそのまま転職の寓話として読むと、「一度外れれば失敗者として終わる」という古い規範を強化する危険がある。しかし同時に、この物語を現代的に読み直すことで、「李徴が虎で終わらざるを得なかったのは当時の社会構造のせいだ」と理解し、現代の私たちはそこから自由であることを自覚できる。『山月記』が今も人を惹きつけるのは、李徴の悲劇に共感すると同時に、「もし現代なら李徴は違う道を選べたのではないか」と想像できる余地があるからだろう。
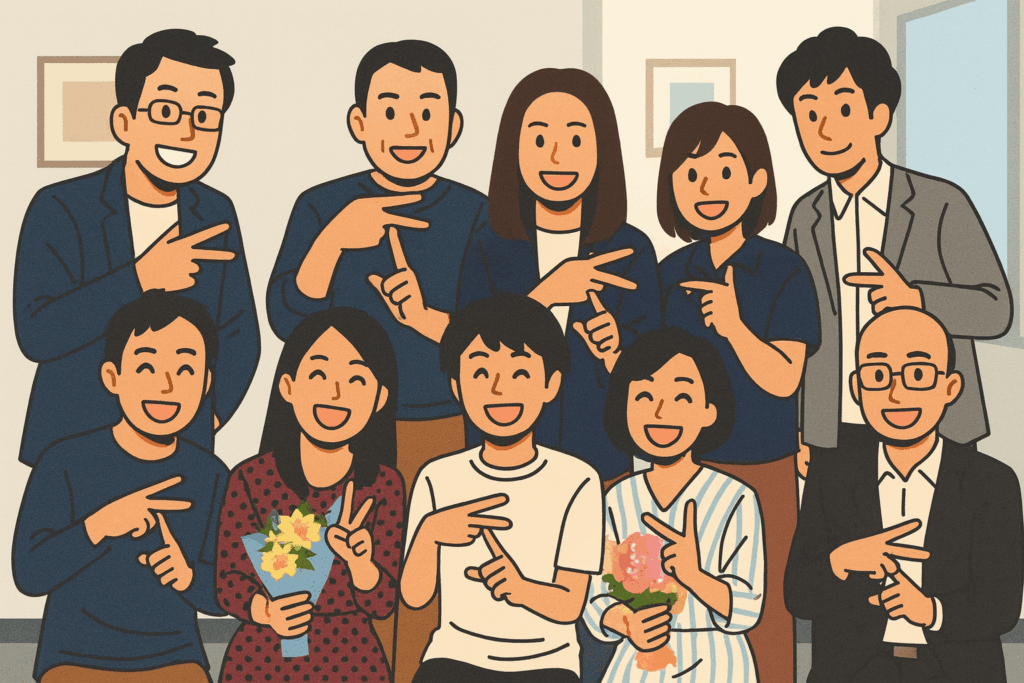
おわりに
私達はいま、虎だろうか。犬だろうか。猫だろうか。馬だろうか?
『山月記』は、社会に出て読み返すと、自分自身のキャリアを考える鏡になる。李徴が虎であった理由を考えることは、私たちがどの動物であるかを考えることにつながっている。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a849c23.b4518340.1a849c24.8f806737/?me_id=1213310&item_id=15847261&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6533%2F9784758436533.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント