「コンビニ人間」(村田沙耶香:作)は、2016年の芥川賞を受賞し、アマゾンや各種の文芸ランキングで常に上位にいる人気作品である。世界各国語にも翻訳されている。
(あらすじ・ネタバレあり)
主人公の木野恵子は、大学生のころから十八年間、同じコンビニチェーン「スマイルマート」でアルバイトを続けている女性である。店では最も古株のアルバイトであり、現在も変わらずコンビニで働いている。
あるとき彼女は、白羽という三十五歳の男性と知り合う。白羽はコンビニで働き始めたものの、サボり癖や問題行動が多く、すぐに解雇されてしまう人物である。木野は白羽に恋愛感情を抱くわけではないが、彼を家に住まわせ、食事を与え、同居生活を始める。
白羽の影響を受けて、木野は一度コンビニを辞め、「普通の社会人」になるために面接を受けようとする。しかしその途中、偶然立ち寄った別のコンビニで、無意識のうちに今までと同じように働き始めてしまう。その瞬間、木野は自分が本当に望んでいるのはコンビニで働くことなのだと再確認し、再びコンビニ店員として生きる決意を固めて物語は終わる。

読者の期待と無風感
芥川賞を取った傑作と評される一方で、本作についてはインターネット上には「何が面白いのか分からなかった」「特に何も感じなかった」という感想も少なくない。私自身も、読み終えた直後は実は、強い感動や共感を覚えなかった。しかし考えてみると、この「何も感じなかった」という感覚そのものが、この小説を読む上で重要な手がかりだったように思う。
物語の冒頭近くで、主人公が子どもの頃から変わっていたという回想が入る。そのため読者は、最初から主人公を「例外的な人物」「どこか異常な存在」として読む態勢を整えさせられる。しかし読み進めてみると、主人公の生活や行動は驚くほど平凡である。長年同じ職場で真面目に働き、生活は破綻しておらず、他人に害を与えることもない。特別な才能や強い夢を持っているわけでもなく、極端な破滅に向かっているわけでもない。悩みも、「将来どうするのか」「周囲からどう見られているのか」といった、ごく一般的なものであり、都市で暮らす一人の大人として見れば、むしろ平均的な位置にいるように見える。
それにもかかわらず、作中のミホや妹、同僚たちは、主人公を「治るべき存在」として扱う。「普通になったほうがいい」「このままではまずい」と、善意から忠告する。その視線は、主人公が危険だから向けられているのではなく、説明しにくい違和感を覚えるがゆえに向けられているように見える。
この構造は、読者側にもそのまま再現される。白羽という人物は、思想的で過激な語り口によって、物語に「何か決定的な事件が起きるのではないか」という予感をもたらす存在である。読者は無意識のうちに、彼が実は危険人物なのではないか、あるいは裏の顔を持っているのではないかと身構える。しかし物語は、その期待を回収することなく、静かに終わる。この肩透かしの感覚もまた、読後に「何も起きなかった」「何も感じなかった」という印象を残す一因だろう。
診断的読み方、平凡、例外化
実際、本作についての感想をインターネットで見ると、「主人公はアスペルガーではないか」「サイコパスなのではないか」「病気だから治らないのでは」といった診断的な読みが数多く見られる。

アスペルガーの人ってこんな風に思ってるんだよ…ていう話だなぁと思いながら読んでいった。
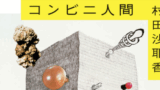
主人公の古倉は子供の頃から何にも愛着を持つことができず、・・・いわゆる”サイコパス”と呼ばれるような人物です。
主人公自身は作中で、「治ること」を拒否しているにもかかわらず、読者はむしろ積極的に「治らない理由」を探し、病名を与えたがる。そこには、「少しでもズレている人を例外として分類したい」「例外だと分かれば安心できる」という欲求が見える。
これは私の体験談であり小説の内容からは逸れるが、以前、平凡な職場に勤務していたとき、会社の同僚たちとの飲み会で、「この会社の人たちって、みんな変わってますよね」と同意を求められたことがある。その場では特に反論しなかったが、内心では「いや、全員自分も含めてだが、ごくごく平凡だ」と感じていた。この経験を思い出すと、『コンビニ人間』で起きていることがよく分かる。人は、平凡な集団や平凡な個人を前にすると、かえって不安になり、「変わっている」という物語を作り出して安心しようとするのではないだろうか。
本作に大きな事件が起きないことも、「何も感じなかった」という感想につながっている。ほかの物語、たとえは有名なもので言うと、西遊記や千夜一夜物語や、多くの少年漫画のように、怪物が現れ、危機が訪れ、解決へ向かう物語では、読者は出来事に引っ張られて感情を動かされる。しかし『コンビニ人間』は、そうした事件駆動の装置を意図的に用いない。物語の途中で、白羽が主人公の家に住み始めた際、同僚たちが色めき立つ場面があるが、そこでは読者自身もまた「何かが起きること」を期待している。しかしその期待は最後まで回収されず、物語は無風のまま終わる。

『コンビニ人間』が描いているのは、「変わった主人公」ではなく、むしろ、「平凡な人を前にして、例外を作り、治そうとし、分類して安心しようとする側」の姿である。読者が「病気なのか」「治らないのか」と考え始めた瞬間、私たちはすでにミホや妹と同じ立場に立っている。そして「白羽と結ばれなかった」「主人公はまたコンビニ店員に戻った」という無風感で肩透かしを食らい、一部の読者は「特に普通だなと。何も共感できなかったし、どこが評価されているのか分からない」という感想を持つこともあるのであろう。しかしそれは、あらかじめ作者によって計算された反応であるとも言える。
素直な感想の出し方
そういう意味で、「何も感じなかった」という感想は、この小説を読み損ねた結果ではなかったと思う。もし学生時代の課題図書として読んでいたなら、「どこにも共感できなかった」「コンビニの客の行動を監視している白羽の行動が怖かった」「数十年も無計画にアルバイトを続ける主人公を見て、自分はこうはなりたくないと思った」といった率直な反応こそが、むしろ自然だっただろう。事件も解決も与えられない物語を前にして、私たち自身がどのように他人を理解し、出来事を整理し、安心しようとするのかを考える。その入口として、「何も感じなかった」という感想は、最も誠実な出発点だったのではないかと思う。
『コンビニ人間』は、共感や感動を強く求める小説ではない。読者の側の視線や欲求を、静かに映し返す鏡のような作品なのである。




コメント